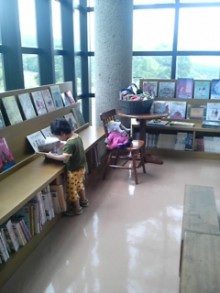そして精米された姉の米が届いた。去年のよりも粒が大きくなったような気がするが、やはり石ころがたまに混ざっている、、、。石ころが混ざっている状態では、絶対に市場には出せんだろうなあ。家族はほほえましい気持ちでそのじゃりっとした石ころを噛む事ができるけど、他人が食べたらまさに苦情の嵐が吹き荒れよう。
今年は米の種類を変えたらしい。きぬひかり?だったかな。こしひかりはやめたらしい。まあ、いろいろやってみるということです。なので、姉から「米食べたら感想聞かせてな!」と電話がかかってきた。母は間違ってずっと「ゆめひかり」と言っていたが、色々な種類の米がありすぎて母は種類が覚えられない。ゆめぴりかってあったよね?混ざったね?

いざ、実食。土曜日のお昼ご飯です。夫も子どもも食べました。いつも待ちきれない子どもが最初に食べるので、記念すべき初食べは2歳の息子です。むしゃむしゃしている息子は、はっと顔をあげて「おいしい!おいしい!」とその後何回も「おいしい」を繰り返していました。あーよかったね。
でも、チョコとかせんべいとか、大概の物は「おいしい」を言うのであまり信用はできないんですが。私も食べてみました。おいしいです。新米の力はすごい。古米より圧倒的に美味しいです。去年の、砂のように小さいお米も、やっぱりちゃんと美味しかったのを覚えています。まだしゃべれなかった息子が、夢中で食べていたのも覚えています。
姉はいつまで米を作る気なのかはわかりません。本人も一番わかっていないのではないでしょうか。突然高校教師をやめ、スペインへ行き、帰って来て環境保護活動と農業を始めた姉。予測不可能な人生、いいのではないでしょうか。姉の旦那様のマイマイ、ねえちゃんに愛想をつかさずいつまでも姉をよろしくお願いします。私は、今姉の作った米を食べられることを幸せと思い大事に食べたいと思います。長生きしてほしいです。ねえちゃん、米美味しかったで。ありがとう。

私の父はマジシャンです。小学生くらいのころからマジックをしてきたそうです。母は、50歳を過ぎて、やっと津のマジッククラブに入りました。「マジックなんかするもんか」と頑張っていた(?)母も、父のマジックの手伝いをすることがあまりに多くなって来て入らざるをえなくなったようです。私と姉は、小さい頃から全くマジックに興味がなく、家中に転がるマジック道具を見ても「また散らかしとる」くらいにしか思ってきませんでした。
家族が決してマジックに積極的ではなく、むしろ疎まれながらも、父はマジックに打ち込んできました。私や母、姉はマジックは好きでなくとも、父がマジックの世界大会などに行く時は嬉々としてついていき、これまで様々な楽しい素晴らしい経験もさせてもらってきています。
ICMコンベンションは、15年前から年1回のペースで父とその友人主催(多分)で開催してきたコンベンションです。私は全く詳しい事は知りません。知りません、が、三重の伊勢、志摩、鳥羽あたりのリゾートホテルを借りて結構大々的にやるので、旅行気分でちょこちょこ参加してきました。今回は伊勢の宝生苑という和風ホテルで開催され、私と息子、姉夫婦、祖母も参加し、姉の旦那さんのご家族まで遠路はるばるやってきてくれました。

その夜の宴会の模様。総勢何人か知らんけど、ずらーっと。大広間貸し切っての夕飯。ここではマジックしません。宴会芸とかじゃありません。また別の舞台で、結構真剣にするんです。審査員とかいますから。父は真っ白なスーツに赤い蝶ネクタイという冗談みたいな格好でうろうろしています。息子はそのじいじを見て嬉しくてたまらんようでした。

年によってはヨーロッパなどからゲストマジシャンを呼んだりしていますが、最近はやはりアジアのマジシャンが多いです。韓国と中国の方がとても多いですね。当たり前ですがマジックの世界でも流行などがめまぐるしく変わっておるようで、カードを使うしっとりとしたものが流行るときもあれば、物語の世界をマジックで表現するものもあり、、、それでもマジックは全世界でこれほどに愛されているのだなあ、という事実。それに、私なんかは驚いたりするのです。
年一回、このような外国の方も巻き込んでの大会を運営していくというのは、並大抵ではないです。父が代表みたいな感じですが、その裏方をすべて回してくれているのが、父が講師を務めているマジッククラブのメンバーの方々です。何教室かあるようで、その方々がボランティアですべてしてくれています。これはすごいことなんです。それに一年費やしているといっても過言ではないくらい、大変みたいです。父も母も連日のミーティングやらで、この時期はずっとふらふらです。メンバーの中でも意見の食い違いなどで諍いがおきたり、メンバーが脱退したり、人間だもの状態で色々あるようです。
私は「そんなしんどいのになんでやるんやろう」とか思ってしまうんですが、そういうことじゃないんですね。しんどくても、やるんです。多くのマジック好きの人々をを繋げ、広げ、温め、そしてまた次に繋げたいという想いがあるんでしょうね。笑って、びっくりして、感心して、数分間のショーの間、人々は目を輝かせている。その瞬間が好きで、大事なんでしょうね。
コンベンションが終わり、ぼろぞうきんのようにふらふらのぼさぼさになった両親ですが、その数日後には、父は新しい会場を探しに行っていました。
うちの親がんばるなあ。

三重の実家に一月半も帰っていました。色々イベントがあって、慌ただしくあっという間に過ぎて行きました。
私が一番楽しみにしていたのは、姉の稲刈りに参加する事でした。姉は住んでいる大阪と、実家である三重を行ったり来たり、家族や旦那さんすべてを巻き込んでどうにか農業を続けています。去年は初めて米を作り、私もそのお米をしばらくいただいていました。姉の米は、とても小さくて、小石が時々混じっていました。出来がいいとは到底言えないのですが、私は姉が米を本当に作ったのだと心底感激しました。その年の稲刈りはそれはそれは大変で、普段はソファから微動だにしない父までもが走り回っていたというのですから、こんな私でも何か力になれるかもしれぬと、2歳の息子も一緒に姉の田んぼに向かいました。
朝6時に、すでに姉は田んぼに向かっていました。母も前日から緊張していて、本当に朝から家中がそわそわ緊張していました。今年は台風がじゃんじゃん三重にも来て、姉はその度に「稲が倒れませんように、倒れませんように」と祈っておりました。家族中が台風情報に一喜一憂し、姉の米を心配していました。稲が倒れると、コンバインでの刈り入れがものすごく大変なのだと、そのとき初めて私は知りました。姉の田んぼには朝から、籾殻をとってくれるテルオじいさんが来ており、姉の米はテルオじいさんの機械を壊してしまう程に不純物が多いから、気をつけて稲刈りをするようにと姉の耳元で繰り返し説明しておりました。この地域の人は、ほとんどがこのテルオじいさんちの機械で籾殻を取るのだということも初めて私は知りました。
午後にはマルオおじさんも来てくれて、時々キクオおじさんも様子を見に来てくれました。私は姉よりずっと長く三重に住んでいたけれど、地域のおじさんの名前をほとんど知らないし、話した事もほとんどありませんでした。なので姉の口から次々と「キクオちゃんがアドバイスくれた〜」とか「テルオちゃんに怒られた〜。」とか、じゃんじゃん私の知らない地域のおじさんの名前が出る事にただただ驚いていました。

朝6時に田んぼに行った姉が、刈り入れをすべて終えたのはなんと夕方6時半。田んぼは小さいものが3つだけ。すぐ下で、姉より何倍も大きい田んぼを刈り入れしていた人がいて、その人は1時間もかからずにすべての稲刈りを終えていました。姉の稲刈りがどれだけ大変かお分かりでしょうか?
なぜこんなに大変かというと、まあ私も全然よく分かってないんですが。姉がど素人だというのはもちろんなんですが、ど素人なのに完全無農薬で米を作っているからなんです。そうすると、稲以外の雑草もものすごくて、稲自体はちんちくりんだったりするのに、他の植物がすごいのです。なんかそうすると色々やっぱりスムーズにいかずに、機械は何度も止まるし、その度に姉はヤンマーの人に電話したり、マルオおじちゃんに聞いたりもうものすごく必死に姉が頑張っているのがわかる。サンドイッチをコンバインの椅子の上で少し食べて、あとは朝6時から夕方6時半まで、なんとトイレにも行ってなかったんです。母はそんな姉の事が心配だし力になりたいのとで、周りの草を刈り続けている。
私と父と、2歳の息子はというと、最初はどうしていいか分からずに軽トラックの中でただじっと姉を見ていた。「あれとって来て、これ買って来て」という願いを聞くとすぐに取ってくるくらいしかできなかった。でもどんどん日が傾いて行く中、私もやっぱり草を刈ったりするようになった。そして、父と一緒に軽トラックに乗ってテルオじいさんのところに借り入れた稲を持って行った。私と父は夕暮れの中「ねえちゃんすごいなあ」とつぶやいたり、テルオじいさんがもう80近いのに、めちゃくちゃ重い米のつまった袋を軽々持ち上げることにただ驚いていた。テルオさんも、キクオさんも、マルオちゃんもみんな還暦をとおに過ぎているのに、みんな力持ちで、ものすごくよく働き、日に焼けて、体には無駄な贅肉がついていなかった。農業をするおじさんたちはあまりにもまぶしかった。
そして、農薬を全く使わない姉の田んぼを刈った時に、あまりにもたくさんの生き物が刈った田んぼの中に住んでいた。稲の無くなった田んぼに一歩足を踏み入れると、私の足に驚いた何百何千の生き物達がいっせいに飛び上がった。カエルもものすごい数、虫もものすごい数、カメもいた、ねずみもいた。あんなにもいっせいに動く生き物たちを私は見た事がなかった。ざわざわと大地を揺るがすような生き物達の姿が忘れられない。
その中で、慣れない大きな機械を動かし、おじさんたちに一生懸命教えを乞い、汗まみれになって、家族みんなを巻き込んで、それでも自分がやるといったら何が何でもやるという、なんだかもう変な生き物に見えて来た姉が、私はただただ大好きであります。
そんな血反吐を吐くような想いで作った米は、たった4俵ほどしか採れずに、みんなに「もう来年は肥料くらい使おうよ」と言われながら、姉はさあ来年はどうするのかな。

本日、息子を連れて表参道で開催されている「Re:女生徒」展へ行って参りました。久しぶりの展示だったので非常に緊張しました。緊張しすぎてなかなか最初名前を名乗れなかったです。
今回の展示は太宰治の書いた「女生徒」という小説を7人のデザイナーさんが装丁を新たにデザインして本の形にして展示するというものでした。私はその中の福田さんというデザイナーの方に声をかけていただいて、イラストを描きました。実際に女生徒という小説を読ませていただいて、ちょっと気を張った眼差しを持った少女が私の頭の中でうつむいたり、はっとした表情をしたりと、昔に描かれたものではないように鮮やかに、生きていました。

で、このような形の本になりました。いやー、デザイナーさんってすごいなあ。大胆に絵をつかってくださって嬉しいです。他の方々の女生徒もほんとうに素晴らしかったです。予想もつかなかった形になって、美しい本達がそこにはありました。

8月の12日まで開催しておりますので、ご興味の湧いた方は是非に。私は搬入作業も搬出作業も参加できずです。展示をしてくださった方々、どうもありがとうございます。そして、忙しいお仕事の傍らに、自らこのような企画を考え実行に移し形にするそのデザイナーさんの情熱に、私ははっと感動しました。子育てを理由に絵から遠ざかり気味の私でしたが、そんなゆるんだおしりをぴしゃりと、でもやさしく押していただいたようなそんな気持ちがいたしました。どうもありがとうございました。
そして、この日は私の古くからの友人3人も来ていただきました。この友人の方々と居る時は私はいつも都会を満喫している気持ちになります。私とお友達でいいのかしら?!っと思うくらいトレンディな友人だからです。いつも私が想像だにしていなかったおしゃれな装いです。赤いリップ、奇麗なブルーのアイシャドウ、どんぐりのようなかわいい帽子、絶妙な丈の黒いパンツ、美しい植物プリントのシャツ。そしていつも私を楽しいおしゃれな場所に連れて行ってくれるのです。だからいつもなんだか地に足のつかないふわふわした夢のような気持ちになります。
私が育った田舎は、小さな喫茶店ができただけで大騒ぎになるような場所です。それを思い出すと、今日私がいた表参道という場所で見たおしゃれな人々は、同じ小さな島国の同じ民族なのに、まるで別の惑星の人々のように見えて不思議でした。でも私のおしゃれな友人は、昔から知っている笑顔で私に笑いかけてくれました。それでとても安心しました。息子も私も少し興奮して、帰りの電車に乗りました。今日は来てくれてどうもありがとう。とても楽しい時間でした。

竹風堂で満足したあと、そこからまた1時間ほど車を走らせて黒姫にある黒姫童話館という絵本のミュージアムに行きました。今回宿泊した斑尾の高原ホテルもそうですが、この童話館も「なんでこんな辺鄙な場所に、、、!」というほどぐねぐねぐねと山道をひたすら走ってたどり着きます。
長野の山奥といえば、一昔前はスキーや別荘ビジネスで盛り上がったでしょうが、今はスキーブームも別荘ブームも過ぎ去りしという感。廃墟になったペンションやホテルがあちこちに見られます。そんな山奥の道なき道をくぐり抜けて、突然狐につままれたようにその童話感は現れます。
すんごい、立派。すんごい絶景。まさに夢物語の世界。現実世界に嫌気がさしたとき、すぐ近くにこんな場所があったらなと思わせます。手入れをされつくした美しく広大な芝生。石畳の道、庭にはヤギさんが数匹。目の前は高原が広がっていて、遊歩道もあります。平日は、おそらくほとんどお客さんはこないと思われるこの山奥に、あまりにも奇麗に手入れされた広大な芝生がなんだか本当に不思議でした。やっぱ夢の国だからね、荒れ果てる訳にはいかないものね。この広い土地をこれだけ手入れするって相当お金がかかってるんじゃないかとか、館内の係のおばさんとかカフェの人件費とか、なんだか心配になりました。余計なお世話だろうけど。でももうかなり昔からある施設だから、寄付とかでちゃんとやっていけるのでしょうね。ちょっとここで働いてみたいなとも思いました。

童話館の建物自体も、そうね、確かに白姫様が住んでいるというよりは黒姫様のお城という感じの堅牢な作り。中の展示は「モモ」で有名なミヒャエル・エンデの資料や長野の民話のお部屋などがあって、ふらっとついでに来るというよりは、「今日は一日ここで過ごす」というくらいの気合いが必要なくらい盛りだくさんでした。
ミヒャエルさんも、日本の長野の山奥に、自分の作品がメインにされているミュージアムが建てられると知って、ちゃんと来日して喜んでくれたようです。サインとかゆかりの品とかたくさんありました。
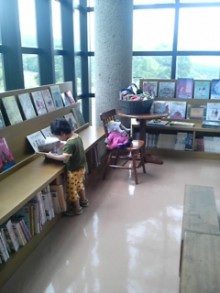
もちろん絵本を読むスペースもあります。この日は平日だったので私たちの家族だけでした。3人占めですね。この絵本スペースはガラス張りのお部屋だったのですが、どちらかというと私は絵本の日焼けが心配でした。夏は相当暑くなる気もしました。でもここのスペースで、私たち3人はしばし自分の好きな絵本を手に取って読みふけりました。自分が昔読んでいた絵本が見つかると、何とも言えない懐かしくて胸を締め付けられるような気持ちになります。
その他には、私の好きないわさきちひろさんの別荘がそのまま残されていて、中を見学できるようになっていました。はー、確かにここなら虫の声か鳥の鳴き声しか聞こえないでしょうからね、制作に集中できるでしょうね。私は怖くて、一人じゃとても住めないけど。
長野旅行はこれで終了。息子は、ほとんどずーっと機嫌が良く、ソフトクリームを毎日食べ、私も山道のうねうねで車酔いした以外は、家事もしなくていいから本当に楽しかったです。夫は長時間ドライブで疲労困憊したようでしたが、家族が機嫌がいいならそれでいいじゃないか。
旅行って本当に大好きです。またどっか行きたいな。